
「えっ、最近の宿題ってChatGPTでやるもんちゃうん?」
令和の小学生の宿題事情に、昭和生まれのおっさんが一石を投じた。
AIに頼った善意の“父の手助け”が、まさかの学校で炎上するとは──
誰が想像しただろうか。
「お父さん、算数わからん」
ある夜、夕飯後のリビング。
「お父さん、宿題手伝って」と、珍しく素直な息子(小5)。
プリントを見ると、「分数のかけ算」と「作文」の2本立て。
おっさん、心の声:

分数……? えーと、分母がどうとか……
作文……なんか最近書いてへんな……
そんな時、ふと頭に浮かんだのは、
いつもブログで使っている「AIの相棒」=ChatGPT。

「こいつに頼んだら一発やろ」
AI、火を吹く
おっさん、得意げにノートPCを開き、こう入力:

「小学校5年生の算数、分数のかけ算の答えをステップ付きで教えて」
即座に完璧な解説が返ってくる。
作文も同様。テーマは「最近楽しかったこと」。

「小5の男子が、遠足に行った話で300字の作文を書いて」
するとAIが、まるで息子が本当に行ってきたかのような
感情表現豊かな作文を生成。
息子は「すげぇぇぇ!!!」と大興奮。

「これが令和の教育や」
翌日、炎上する
数日後、学校から連絡が入る。
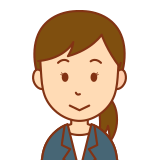
「お父さま、宿題の件で少しお話が……」
学校に出向くと、担任の先生が神妙な顔でこう言う。
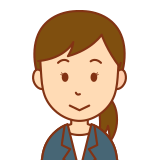
「お子さんの作文ですが、あまりに“構成が完璧すぎる”んです」
しかも、複数の児童が似たような文体・語彙で提出していたと判明。
そのうちの1人が「お父さんが“AIで作った”って言ってた」と白状したらしい。

「まさかの犯人グループ扱いで草も生えんわ」
PTAグループチャットも大荒れ
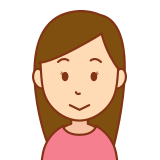
「子どもが自分で考えなくなってしまう」

「ズルしてるのと同じでは?」
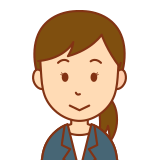
「教育現場の危機です」
PTAのLINEが荒れるなか、当のおっさんはというと…

「……えっ、手伝っただけやん。
ていうかワシがやったんちゃう。AIがやったんや」
反省会:AIは鉛筆を持たないけど、責任は親にある
たしかに、おっさんは悪気がなかった。
でも先生の言葉が胸に刺さる。
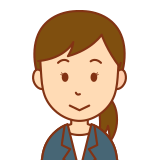
「“考える”プロセスが宿題の目的なんです。
正解より、“どう考えたか”を大切にしています」

──そうか。子どもが「答えを得ること」より、
「悩んで試すこと」こそが、学びやったんや。
おっさん、目からウロコ。
リアルな“父の宿題”が始まる
それからおっさんは、AIの使い方をちょっと変えた。
・宿題はまず自分で考えさせる
・AIを使うときは「答え」ではなく「考え方のヒント」を一緒に見る
・息子とAIと、おっさんの“三人四脚”

「親のほうが勉強してる気がするわ……」
とぼやきながらも、息子の「なるほど!」が増えていくのがうれしい。
まとめ:AIは便利。でも育てるのは親。
AIが教えてくれるのは「情報」だけ。
「学ぶ姿勢」や「考える癖」は、やっぱり親の出番なのかもしれない。

「息子の宿題、ワシも宿題。
一緒にやるから、意味があるんやな」
──おっさん、またひとつAIとの距離感を学ぶ。
おまけ:ChatGPTが教えてくれた“子ども向けアドバイス”

「間違えてもいいんだよ。
自分の言葉で書くことが、いちばんカッコいいからね」

……いや、マジでAIがいいこと言ってて震えるやつ。


