
2025年の節分は2月2日でしたね。通常は2月3日ですが、2025年は立春が2月3日のため、前日の2月2日になったようです。ちなみに2021年も節分が2月2日だったようですが、その時は124年ぶりだったそうです。
そんな知識を得られたところで、今回は節分に関するAIについて教えてもらおうかなと思います。
ということで、今回は「節分に関するAI」を教えてもらおう

今回は神主とAIのプロフェッショナルであるAIコンサルタントの話を聞いてみよう。
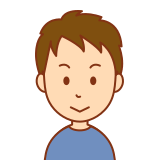
今年も節分が近づいてきましたね。節分は邪気を払って福を呼び込む大切な行事ですが、AIを使って何か新しい取り組みができないかと考えていまして…。どう思われますか?
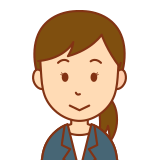
素晴らしいですね!AIを活用することで、節分をより多くの方に楽しんでもらえる機会を広げたり、伝統行事の意義を深く知ってもらえる工夫ができそうです。例えば、以下のようなアイデアがあります:
-
AR体験を活用した豆まき
スマホアプリを通じて、拡張現実(AR)で鬼が出現し、バーチャル豆まきを楽しめる仕組みを作ることができます。お子様や遠方にいる方にも、楽しく節分の伝統に参加していただけます。 -
恵方巻きの最適化AI
恵方巻きを作る際に、地域や家族の好みに応じてAIが具材の組み合わせを提案する機能を提供するのも面白いかもしれません。 -
節分の歴史と習わしを学ぶAIチャットボット
神社のウェブサイトやイベントで、節分の起源や豆まきの由来について解説してくれるAIチャットボットを設置すれば、訪れる方々に伝統の意義を深く知っていただけるでしょう。
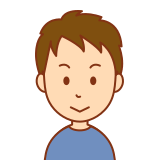
面白いですね!特にARの豆まきは、最近では神社に来られない方や、若い世代にも喜ばれそうです。ですが、神事としての側面を大切にしつつ、こうしたデジタル要素をどう取り入れるかが課題になりそうです。
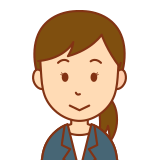
その通りですね。デジタル技術はあくまで補助的な役割と考えるのが良いと思います。例えば、AR豆まきの際に「実際の神社の豆まき映像」と連動させることで、伝統的な雰囲気を残したまま、新しい参加方法を提案することができます。さらに、神社独自の「福を呼ぶお言葉」や「ご祈祷」をAIを通じて音声やテキストで配信するのも効果的でしょう。
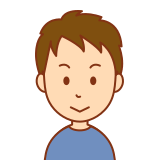
なるほど、それなら伝統を損なうことなく、新しい形で節分を広めることができそうですね。ところで、AIを使って神社の運営自体にも役立つことはありますか?
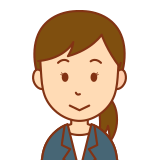
はい、神社運営にも活用できます。例えば:
-
参拝者データの分析
節分の参拝者数や時間帯をAIで分析し、次回のイベントの最適な準備計画を立てられます。 -
予約管理システム
節分の特別祈祷などの予約をAIが効率的に管理し、定員調整やお知らせを自動化できます。 -
オンライン奉納や祈願サービス
遠方の方が祈願を依頼できるオンラインプラットフォームをAIで最適化し、神社の収益を広げることも可能です。
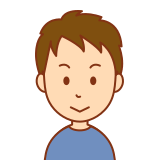
それは非常に助かりますね。今年の節分では少しでもこれらのアイデアを試してみたいと思います。ご協力いただきありがとうございます!
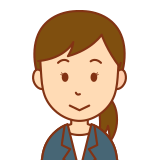
こちらこそ、貴重なお話ができて光栄です。節分がより多くの人にとって意味深く、楽しいイベントになることを祈っています!

お二人、ありがとうございました。
神事という側面からデジタル化やAI化ということは敬遠されそうかなと思いましたが、AIを活用できそうだなと感じました。
神主さんも触れていますが、AR豆まきの発想はなかったですね。幼稚園や保育園のイベントで先生や親御さんが鬼に扮して「鬼は外、福は内」ってやりますよね。子どもが泣いている姿が思い出されますが、ARであれば怖い鬼ではなく、可愛らしい鬼とかも表現できそうなので、家では怖さを和らげて豆まきを楽しむということもできるかもしれないですね。
節分にまつわるAIアプリを考えてもらおう

さて、節分にまつわるAIの話を聞けたところで、節分にまつわるアプリを考えてもらおうかな。

節分にまつわるAIアプリケーションを考える際、日本の文化や伝統行事のデジタル化、楽しみの増加、さらには教育的な要素を取り入れることがポイントです。以下のようなアイデアを提案します。

1. 節分豆まきシミュレーター
- 概要: 家族や友人と仮想空間で豆まきを楽しむアプリ。
- 機能:
- AR(拡張現実)を利用し、スマートフォンやARゴーグルで鬼を部屋に登場させる。
- ユーザーがスマホを振ると、画面上で豆を投げられる。
- 投げた豆の正確さやスコアをAIが解析し、結果をランキング形式で表示。
2. 恵方巻きAIガイド
- 概要: 恵方巻きを食べる際、今年の恵方を正確に教えてくれるアプリ。
- 機能:
- 方位センサーを活用してスマホが正確な恵方を指示。
- 食べている最中に願い事を入力しておくと、後からその願いを元にしたポジティブな通知を送る。
- AIが各ユーザーの好みに合わせた恵方巻きレシピを提案。
3. 節分教育AIアシスタント
- 概要: 子供向けに節分の歴史や意味を学べるインタラクティブな教育アプリ。
- 機能:
- 節分に関するクイズ形式のゲームを提供。
- 鬼のキャラクターが話し相手となり、ユーザーが質問すると節分や日本の文化について答えてくれる。
- 節分の地域ごとの習慣や豆の種類に関する情報を提供。
4. パーソナライズド節分イベントプランナー
- 概要: AIが個々の家庭やコミュニティに合わせた節分イベントを提案。
- 機能:
- 家族構成や好み、スケジュールを基にした最適なイベントプランを作成。
- 地域の店舗から鬼のお面や豆を注文できるサービスと連携。
- 地元の神社や文化施設で行われる節分イベントをおすすめ。
5. 鬼の性格診断AI
- 概要: 自分が「どんな鬼に似ているか」を診断するエンタメ要素のあるアプリ。
- 機能:
- 簡単な質問に答えると、AIが性格分析を行い、鬼の種類や特徴を診断。
- 診断結果をSNSでシェアする機能付き。
- ユーザーの鬼キャラクターを生成し、ARで鬼役として豆を受け取れる。
6. デジタル豆収集イベント
- 概要: ポケモンGOのように街中を歩いて豆を集めるゲーム。
- 機能:
- 節分の日限定で、街中のランドマークに仮想の豆が出現。
- AIが歩行距離や収集スコアを記録し、健康管理のデータとしても活用可能。
- 集めた豆でAR鬼と戦うバトルモード付き。

日本文化への理解を深めつつ、伝統行事を現代の技術で楽しめそうだな。豆まきをゲームにするのも面白いかも。
鬼の性格診断を見て思ったけど、鬼の種類ってそんなに多いのか?別のことに興味が移ってしまいましたが、あなたは、どれが一番魅力的に感じましたか?
今度、別の行事についてもAIと紐付けて聞いてみようと思います。


